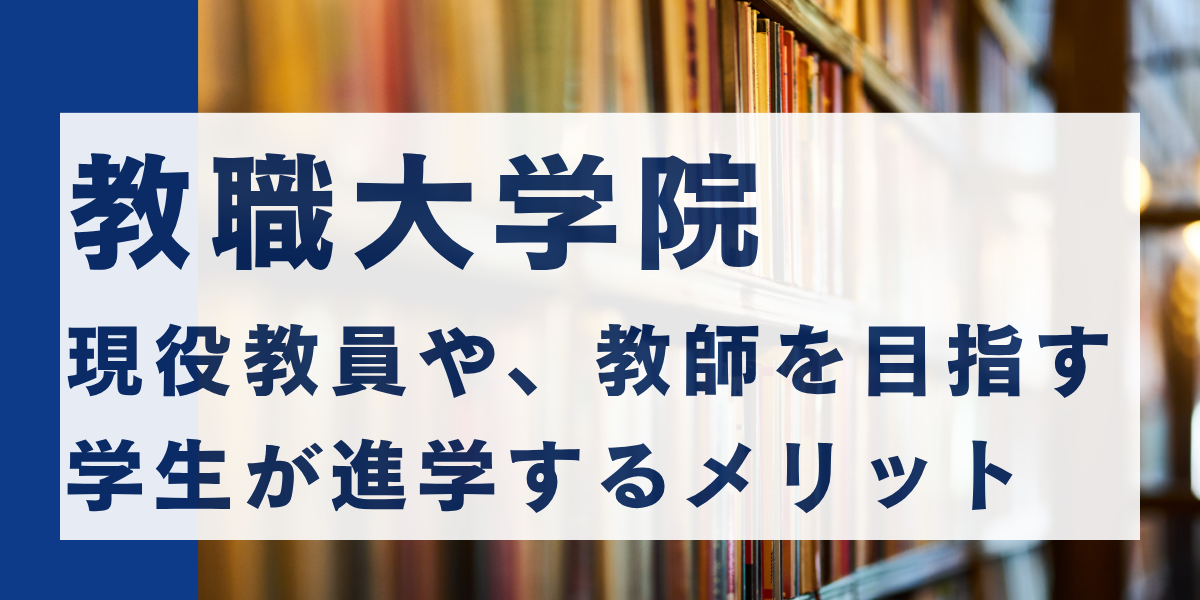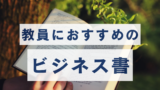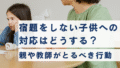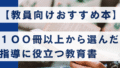私は現役教員です。そんな私は、教員でありながら教職大学院に通っています。
教職大学院への進学は、現役の教員にとっても、これから教員を目指す学生の皆さんにとっても、大きなメリットがあると感じています。
この記事では、現役教員として実際に教職大学院に通っている私の立場から、教職大学院に現役教員や教師を目指す学生が進学するメリットについて解説していきます。
そもそも教職大学院(専門職学位課程)とは?
教職大学院は、高度な専門性と実践力を持つ教員を養成するために、2008年度に創設された専門職大学院です。正式名称は「専門職学位課程」の「教職実践研究科」といい、従来の教育系大学院とは一線を画しています。教育の理論研究だけでなく、学校現場での実践的な指導力や応用力を徹底的に身につけさせることを目的としています。
特徴は「実践性」を重視していること
最大の特徴は、実践性の重視にあります。カリキュラムは、知識の修得に偏るのではなく、学校現場での課題解決能力を高めることに重点が置かれています。具体的には、授業の組み立て方、生徒指導、学級経営、保護者・地域との連携、そして学校組織運営など、教員として直面する実務的な内容が深く扱われます。
対象者は主に「現職教員」と「ストレートマスター」です。ストレートマスターとは、大学の学部からの進学者で、教員を目指す学生のことです。
「現職教員」は、教育の専門家として、指導力を更に向上させ、学校改革を担える中核的な教員(ミドルリーダー)となることを目的としています。都道府県の教育委員会から派遣されている教員もいます。私もその1人です。
「ストレートマスター」は、学部で教員免許を取得した者が、採用前に実践的な指導力を身につけ、即戦力として活躍できる教員になることを目的としています。
2年間の修業期間で「教職修士(専門職)」の学位が授与される
教職大学院の標準修業年限は2年間で、所定の単位(通常45単位以上)を修得し、特に、学校における実習(インターンシップ)を重視した教育課程を履修する必要があります。これを修了すると、「教職修士(専門職)」という学位が授与されます。この学位は、教育界における高度な専門的知識と実践力を有していることの証明となります。
設置の背景
教職大学院の設置は、社会や技術の変化、いじめや不登校など複雑化する教育課題に対応できる、質の高い教員を安定的に養成する必要性から生まれました。これにより、教員養成システムは、学術研究中心の「修士」課程と、実践的指導力育成に特化した「教職修士(専門職)」課程の二層構造となりました。教職大学院は、学校教育の質の向上と教育現場の専門性強化に不可欠な役割を担っています。
現役教員にとってのメリット
ここからは実際に教職大学院に通っている私が実感しているメリットについて解説していきます。
様々な学校や授業を参観できる

現場で働いていると、日々の業務に追われ、自分の学校以外や自分以外の人の授業に目が向くことがあまりないという現状があります。しかし、教職大学院に通うことで、他の学校や他の人の授業をたくさん参観できます。
様々な学校や、様々な実践をしている方の授業を参観することによって、学びを深めることができます。特に、日本全体の中で先進的に新しい取り組みをしている学校を見ることによって、「こんな視野が、こんなことがあったのか」「こんな新しいことができるんだ」という風に視野が広がることにつながります。
また、自分とは全く違った授業に対する考え方や、ICT活用を含めた新たなやり方に気づくことができます。これらの新たな知見は、日々の自分の実践にすぐに活かすことができるという点で、教職大学院に行く大きなメリットであると感じられています。
経験を生かしてより深い研究ができる

教職大学院に通う最も大きなメリットの一つは、自分のやりたい研究に専念できるという点です。そもそも教職大学院に入学する際の大きな目的の一つは、自分が研究したいことをすることです。
設定される研究テーマは人それぞれであり、例えば、学校教育における学級経営や、特定の教科の授業力向上を目指すもの、子どもに視点を当てた教育に関する研究、あるいは職員の研修や教員育成に焦点を当てるものなど、本当に様々です。
現職教員は、原職教員という立場を利用して、研究の追求のために必要な実践を実際に所属している学校で行っていくことができます。授業を実践し、その実践から得られたフィードバックをもとに研究を進めるという、より実践的な研究を進めることができる点が非常に大きなメリットとなります。
最新の教育動向を知ることができる

教職大学院での学びを通して、現場ではなかなか触れられない最新の教育動向を知り、視野を広げることができます。
例えば、先進的に新しい取り組みをしている学校を見る機会を得ることで、自身の教育観や実践の幅が広がります。また、他の教員の研究や実践に触れる中で、ICT活用を含めた新たなやり方などに気づくことができ、最新の実践を取り入れるきっかけになります。
たくさん本や論文を読める
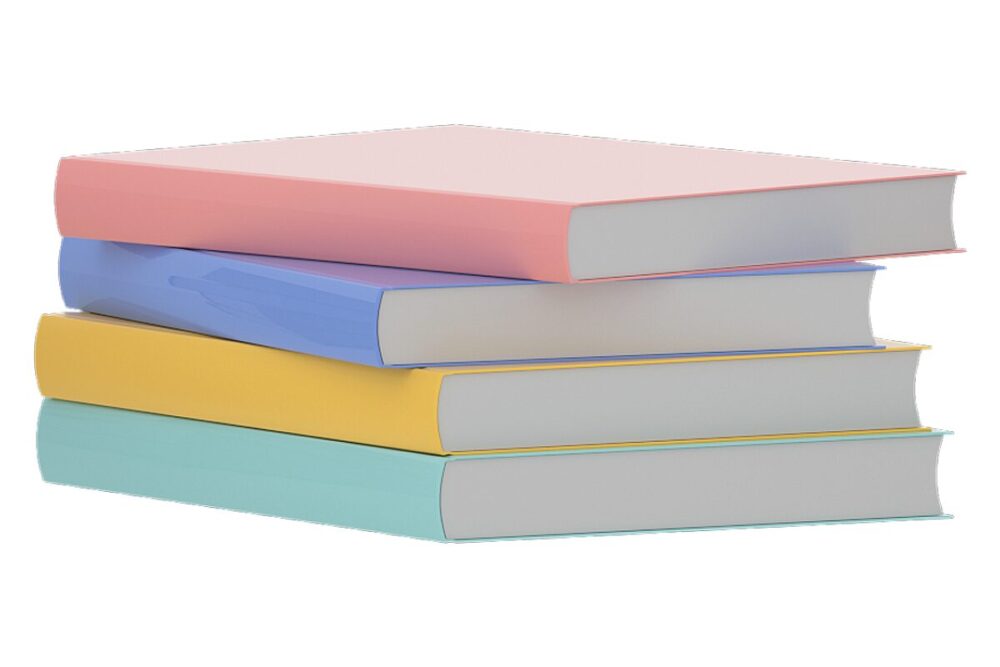
教職大学院に通うことで、たくさんの論文や本を読むことができます。
もちろん、教職大学院でなくとも読書は可能ですが、教職大学院に行くことによって、平日も勤務時間の間に、研究として多くの文献を読むことができ、かなりの時間を文献を読むことに割くことが可能になります。これにより、本を読む時間をより多く確保できます。
読める文献の種類も幅広く、教育系の本はもちろんのこと、一見教育とは関係のないビジネス書、そして論文(自分の研究に関係するもの、しないものを含め)など、幅広く知識を得ることができます。
私がおすすめする本については、以下の記事で紹介していますのでもしよければお読みください。
教員を目指す学生にとってのメリット
大学4年生から教職大学院に進学を考える教員志望の学生にとっても、大きなメリットがあります。
教員になるための非常に濃密な研修の場として、教職大学院を活用することができます。
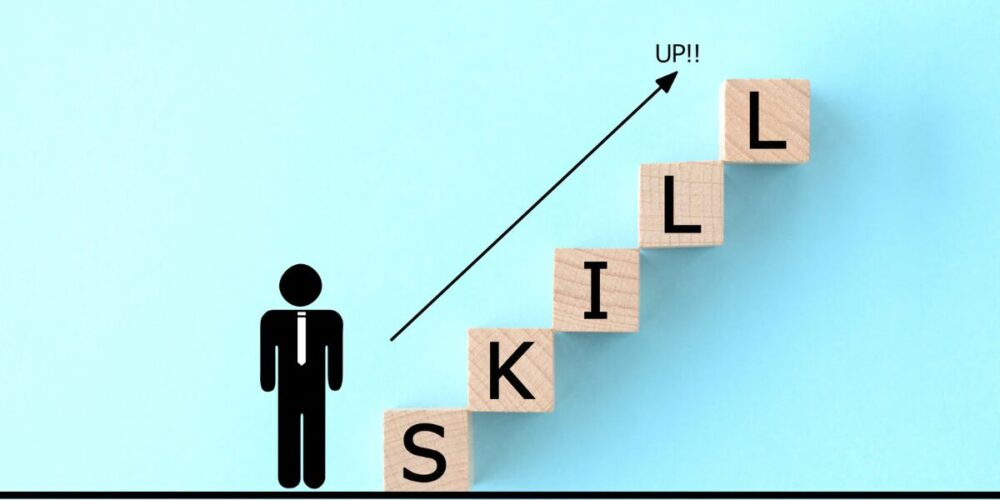
教員は免許を持って採用されるため、一般企業のように4月に入社後に長期の研修期間が設定されているわけではなく、4月からいきなり教壇に立たされる現状があります。
しかし、教職大学院で2年間、じっくりとより実践的な学校教育について学ぶことで、すぐに教壇に立つのではなく、2年後教壇に立つことを想定して自分の知見を深めることができます。これは、2年間のじっくりとした研修期間があると捉えることもでき、非常に大きなメリットです。
また、大学院や都道府県によりますが、大学院進学という条件のもとで、大学4年時に合格した教員採用試験の結果が2年間猶予されるという制度がある場合があります。この制度を利用すると、他の大学4年生と同様に教員採用試験に合格した後、2年後の着任を確約された上で大学院で2年間学ぶことができます。これは学生にとって非常に大きなメリットのある制度です。
最後に
ここまでお読みいただきありがとうございました。
この記事が、教職大学院について理解するきっかけとなったら嬉しいです。