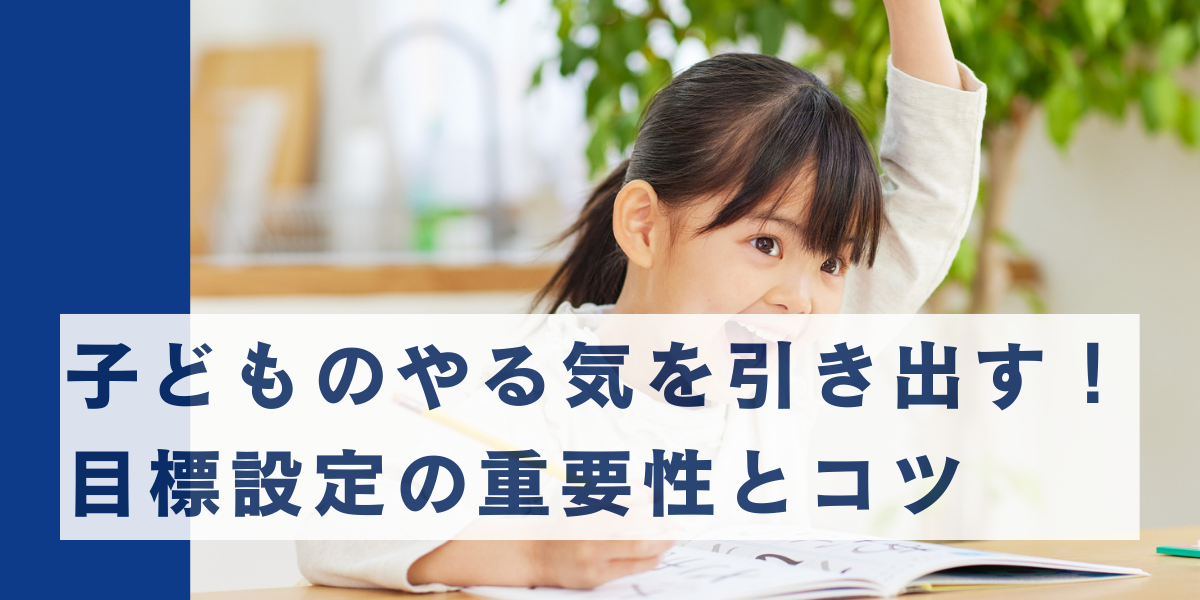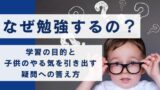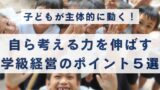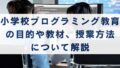学習、習い事、趣味など、子どもにやる気をもって活動してほしいと考える親は多いと思います。
しかし、子供はなかなか親の思うようにはやる気にならないもの…。
最終的には子供自身から湧き出てくるものがやる気ですから親にはどうすることもできませんが、サポートすることはできます。それが、「目標設定」を支援してあげることです。
この記事では、これまで学習塾講師や教師として多くの子どもたちにかかわってきた経験から、子どものやる気を引き出すための子どもの目標設定の重要性とコツについてお伝えしていきます。
目標設定の重要性(なぜ大切なのか)
「なんのために」が明確になることで、やる気が出る

目標を設定することで「なんのために」が明確になり、やる気につながります。これは、子どもも大人も同じだと思います。
何のためにやっているのかがはっきりしていれば、子どもはやる気になって一生懸命に活動します。
例えば、
- 大会で優勝するために、練習を頑張ろう
- テストで100点を取りたいから、勉強しよう
などです。逆に、目標がないのに、ただただやらなければならないことをこなしていくのは子どもにとってはとてもつらいことだと思います。これは、我々大人も同じだと思います。
「自分はどうなりたいか」を考えることで自主性が育つ
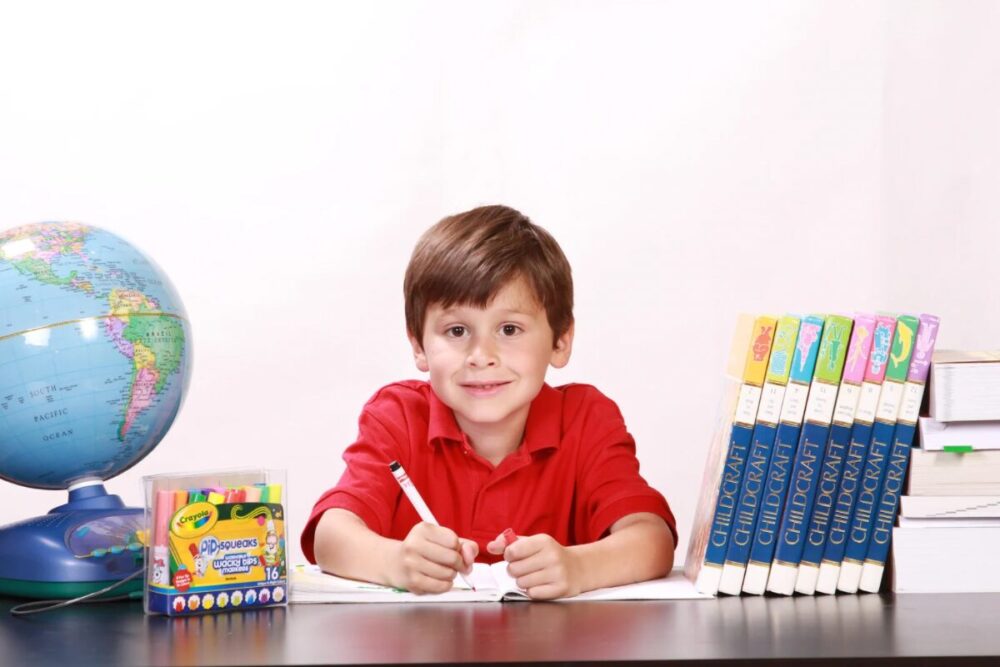
目標を子どもが自ら立てるということは、「自分はどうなりたいのか」を考えることであり、子どもの自主性を育てることにもつながります。
子どもが自ら「自分はどうなりたいか」などと考える機会はなかなかありません
だからこそ、目標設定の機会を大人が設定してあげることによって、子どもが自分自身のことを考える貴重な機会となります。自分自身のことを考える機会は、自主性を育てることにつながると思います。
学級経営においても、「自分たちのことを自分たちで考えていく」ことは、子どもたちの自主性を高めるために私は重要視しています。そのことについては以下の記事に書いていますので、これをお読みの教員の方は是非お読みください。
「目標達成のために何をすればよいか」と計画する力が育つ
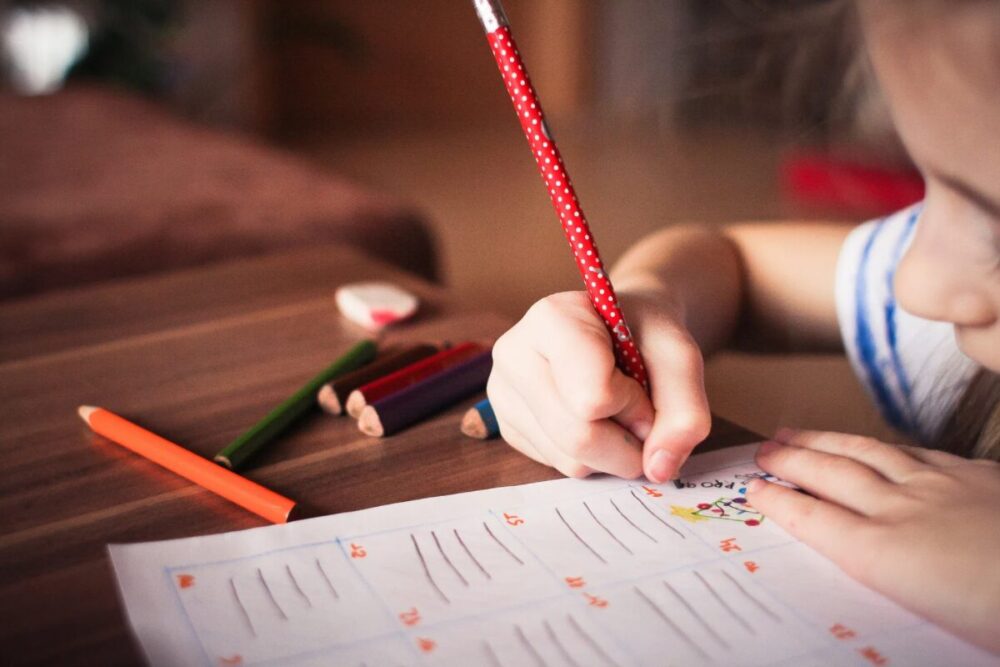
目標設定は、なりたい姿を思い描くだけでなく、そのためには何をすればよいかという具体的な行動を考え、計画することにもなります。
そのため、計画する力が育つことが期待できます。
目標設定のコツ3選
ここからは、子どもが目標設定する際のコツを、3つに整理してお伝えしていきます。
子どもが自分で決める

1つ目は、「子どもが自分で決める」です。
そんなこと当たり前だと感じる方も多いかもしれませんが、子どもたちを見ていると意外と自分で決めていないケースがあります。
例えば、「親に、90点以上取れたらおもちゃを買ってあげると言われました。」という、よくあるパターンで考えてみましょう。
一見、子供は「おもちゃが欲しい」ために「90点をとる」という目標を設定したように見えるかもしれません。しかし、「90点」という点数を設定したのは誰でしょうか?…親ですよね。目標の設定で大事なのは、
- 前回の点数は何点だったか?
- 今回の単元は前回と比べてどの程度の難易度だったか?
- それを踏まえると、自分は今回何点を目指すのが良いか?
というように、自分で考えて目指す目標を設定することです。
目標設定にあたり大人からのアドバイスは必要ですが、最終的には子どもが自分で決めることが大切です。人から決められた目標では、継続したやる気を引き出すことはできません。
小さな目標を立てる

2つ目は、「小さな目標を立てる」です。大きな目標を立てることは素晴らしいことですが、子どもにとっては目標が大きすぎると、それに向けてのステップを考えづらくなってしまいます。これまでの自分から少しだけ背伸びしたくらいの目標がちょうど良いでしょう。また、目標は具体的であればあるほど良いでしょう。この後の「何をするか」を考えやすくなります。
そのために何をするかという具体策を考える

3つ目は、「そのために何をするか?」という具体策を考えましょう。目標を立てただけで終わってしまっては意味がありません。目標を達成するために具体的に何をするのかを考えるところまでが「目標設定」です。
- テストで100点を取りたい → そのためにどうする?
- 大会で地区優勝したい → そのためにどうする?
- 忘れ物をなくしたい → そのためにどうする?
そこを考えることで、具体的な行動の変容へとつなげていくことが大切なのです。
立てた目標は子どもと親で共有

立てた目標は、ぜひ子どもと親で共有しましょう。目標に対する子どもの取り組みに対して、日々励ます声掛けを行えば子どものやる気向上につながるからです。子どもが立てた目標について、寄り添いながら見守り、一緒に達成を喜んであげましょう。
ただし、しつこく聞きすぎたり計画に介入しすぎたりしないように注意してもらいたいです。子どものやる気を低下させることにつながりかねません。
目標設定とふり返りをくり返して習慣化する
目標設定とふり返りは、何回もくり返し行うことが大切です。
目標設定は、年の初めや学期ごとに行うことが多いイメージがありますが、節目にこだわる必要はありません。小さな目標を一つ一つ日々達成していくことを目指し、結果とふり返りを行い、その後また新たな目標を設定するという流れを繰り返すことで習慣化することが必要です。
計画(Plan)→実行(Do)→ふり返り(Check)→改善(Action)
という、PDCAサイクルといわれるサイクルです。目標設定とふり返りを繰り返すことで、このサイクルを習慣化することで、子どもが自ら目標に立ち向かっていくための基礎が身に付くと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。「目標設定」を通して、お子様のやる気が向上し、様々な活動に前向きに取り組めるようになることを願っています。