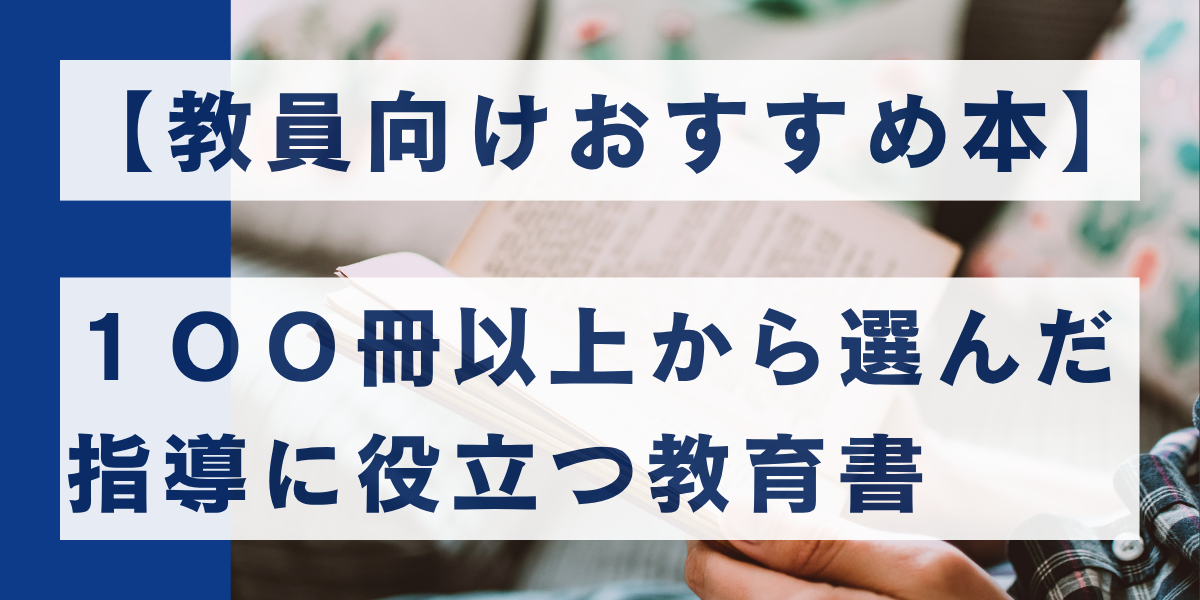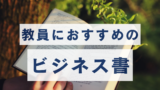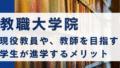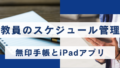読書は社会人が学ぶ上で、最もオーソドックスな手段といえるかもしれません。
教員の方は、「教育書」を読むことで、教員としての指導や授業づくりについて専門的に学びを深めることができます。
この記事では、社会人になってから100冊以上の本を読んできた私が、これまでに実際に読んだ本の中から、教員の方におすすめの本を「教育書」に絞ってご紹介します。
読書は教員にとってどのように役立つのか
学級経営や授業づくりなど、専門的な学びを深めたい場合には「教育書」を読むことでまとまった知識を得ることができます。
私は「教育書」だけでなく「ビジネス書」も読むことにしています。一見教育に関係していない情報でも、知見を深めることで間接的に教育にも良い影響があります。
今回の記事では「教育書」について紹介していきますが、そういった意味ではビジネス書を読むこともおすすめです。私がおすすめする「ビジネス書」については以下の記事にまとめているので、もしよければお読みください。
教員におすすめの教育書5選
ここからは、教員になってから100冊以上の本を読んできた私が、実際に読んで役に立ったおすすめの教育書について紹介していきます。
AさせたいならBと言え 心を動かす言葉の原則
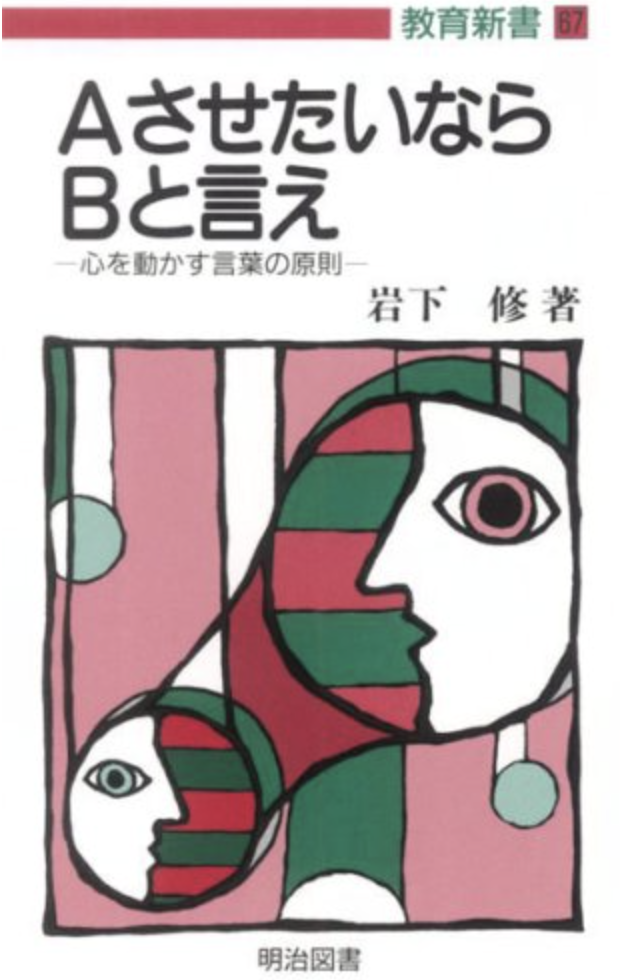
『AさせたいならBと言え ‐ 心を動かす言葉の原則』(著:岩下修)では、人に「Aをさせたい」(行動させたい)場面で、直接「Aしなさい」と命じるだけでは、相手の心は動かず動きにくいため、代わりに「Bという言葉」を使って相手の頭を使い、主体的に動き出させることが提唱されています。
この「B」とは「物・人・場所・数・音・色」といった具体的でゆれの少ない手がかりを含む表現であり、これを使って相手のイメージをうごかし、“知的に動く”状態をつくることがポイントです。
たとえば「静かにしなさい」ではなく「おへそをこっちに向けて」など、具体的で意外性のある表現を用いることで、相手の意識が“図”として浮かび上がり、動きやすくなるなどが紹介されています。
つまり、行動を引き出すには「何をさせたいか(A)」ではなく、「どう言えば相手の頭と心が動くか(B)」を設計する。そうした言葉選びが、子どもにも大人にも有効な“心を動かす言葉の原則”です。
我々教員は、子どもたちに指示を出すことが多いです。してほしい行動を言葉でストレートに伝えるだけでは、なかなか上手くいかないことを経験することも多いでしょう。この本の内容は、どれもなるほどなと感心させられます。
この本は、教育の「プロ」としての大切な「技」を教えてくれる本です。若手教員からベテラン教員、さらに教員を目指す学生に至るまで、教育に関わる人ならば一度は読んでおいた方がいいと思える一冊です。
一度読んだら絶対に忘れない数学の教科書
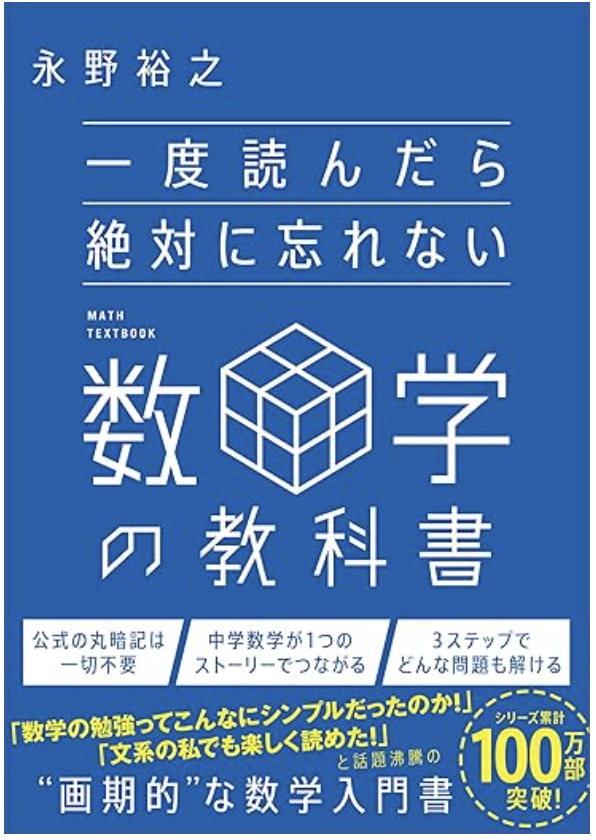
この本は、中学校の数学科教員および小学校で算数を指導する教員におすすめする本です。
本書では主に中学生で扱う内容についての、詳しい数学的背景等についてとてもわかりやすくまとめられています。数学が専門である私が読んでも、まさに目からウロコという内容が盛り沢山です。
小学校で算数を教える際にも、単元の学習の前にその単元の数学的背景を確認し、授業に深みをもたせるために活用できます。
また、これは「一度読んだら絶対に忘れない」シリーズとして他の教科についても出版されているのでそれぞれの専門教科のものを手にとっていただけると学びが得られるのではないかと思います。
教科の一人学び「自由進度学習」の考え方・進め方
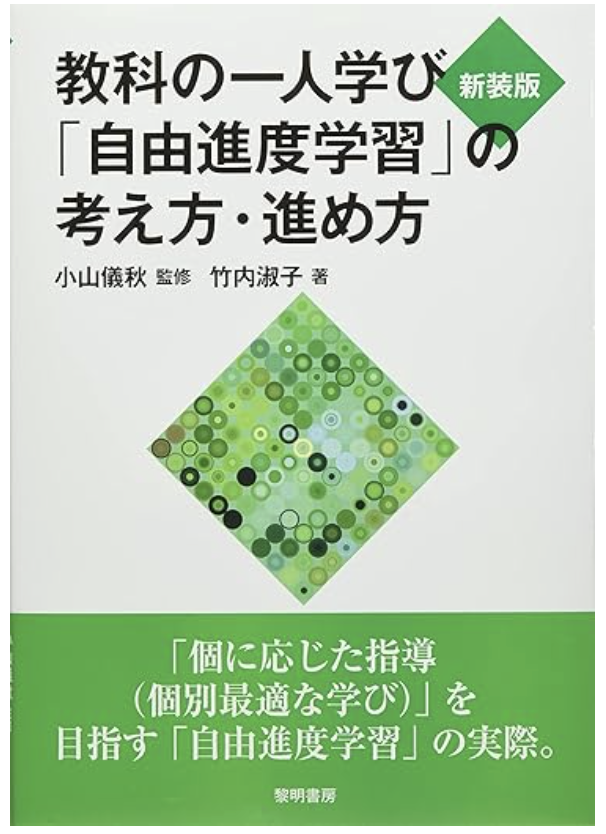
竹内淑子氏の「教科の一人学び『自由進度学習』の考え方・進め方」は、自由進度学習について学びを深めたい教員にピッタリの本です。
- 「自由進度学習」が流行っているけれど、どうやればいいのかよくわからない
- 「自由進度学習」をやってみたけれど上手くいかない
- そもそも「自由進度学習」ってなんだ?今更聞けない
などの教員の皆さんにおすすめできます。本書で取り上げている、愛知県にある「緒川小学校」は何十年も前からこの「自由進度学習」に取り組んでおり、そこで培われたノウハウが本書に詰まっています。
自由進度学習についての書籍は何冊もあり、実際に読みました。あくまで主観ではありますが、本書を読んでおけば間違いないだろうと思います。
学校の「当たり前」をやめた。
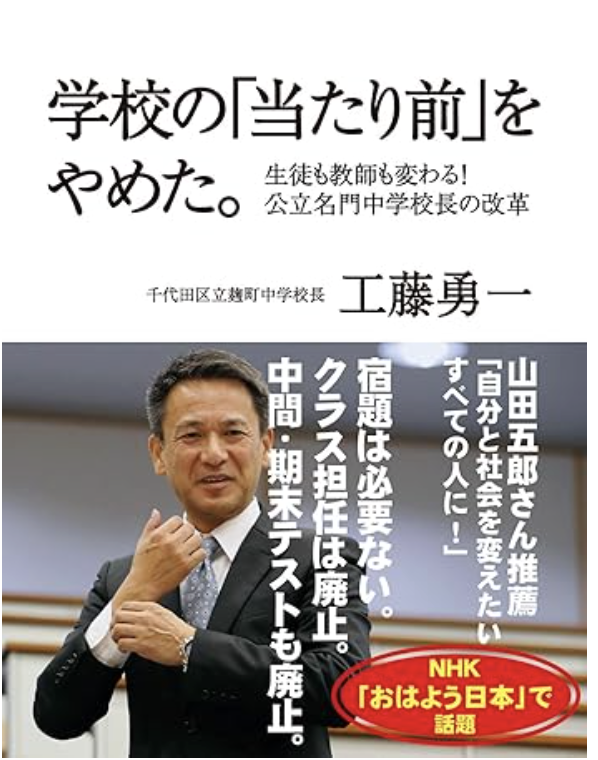
工藤勇一氏の「学校の『当たり前』をやめた。」は、学校教育において宿題・定期テスト・固定担任制・校則などの「昔からの当たり前」の制度が、もはや目的を果たしておらず、むしろ生徒の自律や主体性を阻んでいるという問いかけが主軸となっています。
著者が校長を務めていた公立の麹町中学校において、「宿題を出さない」「中間・期末テストをやめる」「固定担任制を廃止する」「生徒が運営側に入る体育祭など行事の見直し」など、学校の“当たり前”を大胆に手放す改革が紹介されています。その根底にある考え方は、「学校の存在目的は、生徒が社会の中で自ら考え、動ける=自律できる大人に育つこと」であり、そのために手段(宿題・テスト等)が目的化してしまってはいけない、というものです。
また、改革の鍵として「目的(何を育てたいか)を明確にし、手段を一つひとつ問い直す」「生徒・教師ともに当事者意識を持つ」「既存制度に対して“なぜ”を問い続け、固定観念に縛られない組織づくり」が挙げられています。
本書についての私のスタンスは、
考え方には大きく賛同するが、一定の疑問も残る
というのが正直な所です。というのも、著者の工藤氏が去った後の同校をみると、もとの体制に戻るといういわゆる揺り戻し的な動きを見せている部分があるからです。なぜ、揺り戻しが起こったのかという点については、考察が必要だと思います。そのため、安易に工藤氏または現在の体制を批判することはできません。
そんな私がこの本をおすすめする理由としては、教育界において様々な意見が出されるこの改革について、教員である以上は少なくとも知っておく必要があると思うからです。安易に同じように真似すればいいという考え方は危険ですが、少なくとも知っておく必要はあるでしょう。
また、このような議論ができるのも、工藤氏を中心とした本書に書かれているような取り組みを実際に実行されたからこそであり、その点は大いに評価されるべきです。
繰り返しますが、私は本書の内容について全肯定の立場ではありませんが、今後の学校教育を考えていく上での大事な視点を与えてくれるという意味で一読してほしい、おすすめの本といえます。
思考する教室をつくる 概念型カリキュラムの理論と実践
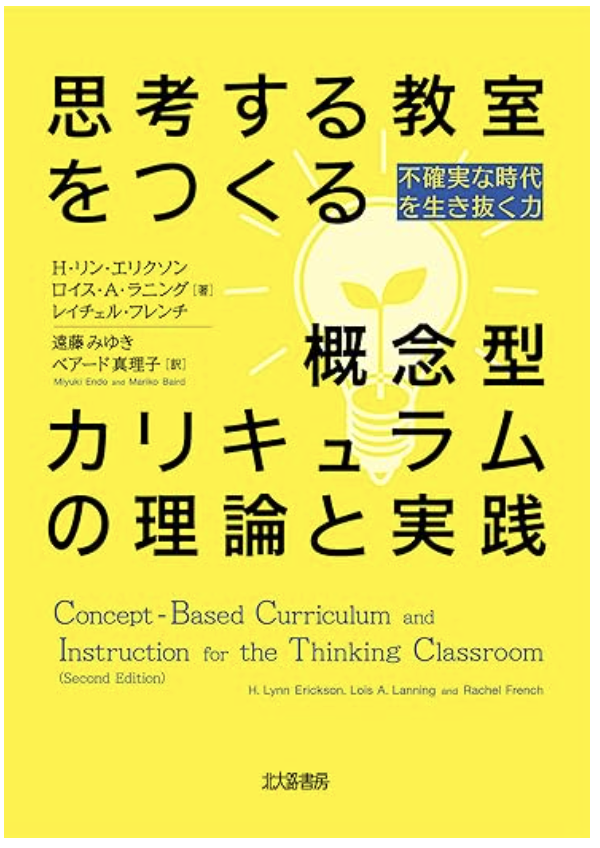
『思考する教室をつくる 概念型カリキュラムの理論と実践』(著:H・リン・エリクソン 他/訳:遠藤みゆきほか)は、AI・情報化時代において「知識を暗記で終わらせず、新たな状況へ転移可能な“活きた知識”を育てるにはどうするか」を論じています。まず、伝統的なカリキュラムが「トピック→知識・スキルの習得」という流れに偏りがちであるのに対し、本書が提唱する「概念型カリキュラム」では、事実やトピックを手掛かりに、時や場所を超えて通用する「概念」、それらをもとに導き出される「一般化」「原理」を学ばせることが重視されます。
また、指導のためには「知識の構造」と「プロセスの構造」という二つの視点を整え、単元を設計し、演繹・帰納を活用しながら「探究」学習へと展開することが示されています。最終章では、教師自身が「概念型マインド」を醸成し、実践・振り返りを通して成長していく必要性が語られています。
学習者が「この学びは何のためか?」「この学びから何が抽出できるか?」を自ら問い、深く思考していける教室づくりを目指す視点が提供されます。
本書は、授業づくりという視点からたいへん大きな学びを得られます。授業づくりを行っていく上で重要なポイントがおさえられており、これからの時代を生きる子どもたちに対してどのような授業を実践していくべきかという点において、深めることができます。
この本を読んでから、授業づくりに対する考え方が変わりました。その教科の「本質」を捉えて単元を構成していくことの大切さに気づかせてくれる一冊です。
まとめ
ここまで、私がこれまでに実際に読んだ本の中から、教員の方におすすめの仕事に役立つ教育書を紹介してきました。
ここで紹介した本以外に、教員におすすめの教育書などがありましたら、お問い合わせフォームか、Xへの投稿などで教えて頂けると嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。