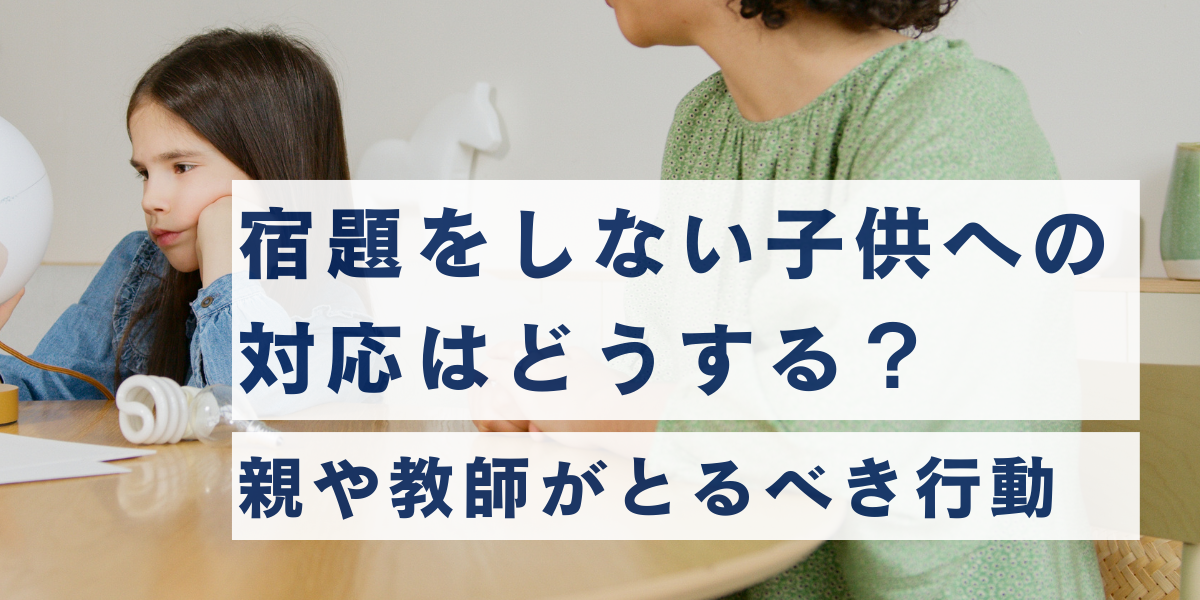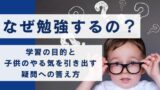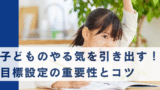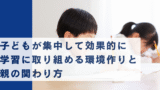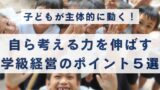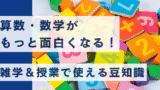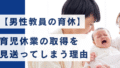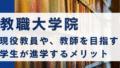小・中学生の親や教師にとって、「宿題をしない子供」への対応は悩ましい問題でしょう。
親や教師の対応次第では、かえって逆効果となり、子どもが宿題から遠ざかってしまうこともあります。
この記事では、宿題をしない子供に、親と教師のそれぞれの立場からどのように対応したらよいかを書いていきます。
宿題をしない子供への親の対応
まずは、親としてどう対応したらよいかについて書いていきます。
なぜ学習するのかという学習の目的を子どもと一緒に確認する
まずは、学習することの目的を子どもと共有することが大切です。
なぜ学習するのか?がわからないまま、とにかくやれと言われたことをやるということ程辛いものはありません。これは、大人でも同じだと思います。
ですからまずは、「なぜ勉強するのか?」を子どもと確認することが大切でしょう。学習の目的は人それぞれ違っていいと思いますが、改めて「何のため?」と考えると難しいもの…。以下の記事では、なぜ勉強するの?という学習の目的について、いくつかの例を挙げています。是非参考にしながら、お子様と一緒に考えてみてください。
子どもの目標設定をサポートする
なぜ学習するのか?ということとも関わってきますが、子供が宿題にしっかりと取り組むためには、ある程度の目標を設定することが有効です。目標設定といっても様々で、
- 資格試験などの「合格」を目標にする
- 定期テストでの「点数」を目標にする
- 毎日継続して頑張るという「態度」を目標にする
などが考えられます。
ただ、どんな目標にするにしても大切なのは「自分で決めた目標である」ということ。目標設定のコツについては以下の記事を参考にしてください。
家で集中して宿題に取り組める環境づくりをする
子供がしっかりと宿題に取り組むためには、子供が集中して学習に取り組める環境作りが欠かせません。
机や椅子、静かな空間などの「物理的な環境」だけでなく、親が子供の活動を見守るなどの環境を整えていくことも重要です。
子供が集中して学習に取り組める環境づくりについては、以下の記事を参考にしてください。
宿題をしない子供への教師の対応
次に、教師としてどう対応したらよいかについて書いていきます。
宿題の目的を明確にし、子供や事前に伝える
これは、親の対応の所にも書いたのですが、目的がわからないことを一生懸命にやれといわれることはとても苦痛なことです。
「あなたは教員として、なぜ宿題を出しているのですか?」
この質問に答えられないのであれば、宿題について今すぐに考え直さなければいけません。昔から当たり前のように宿題は出されてきているので「何のためにといわれても…」と思う方もいるのかもしれませんが、今の時代それでは通用しないと言ってよいでしょう。
「子供が宿題をしない」と悩む前に、「教員として自分はなぜ宿題を出しているのか?」を自身に問い直しましょう。私が考える宿題を出す意味は以下の記事をお読みください。
考えた結果、「宿題を出さない」ということも私はありだと思います。いずれにしても、目的を明らかにすることが大切です。宿題の目的が明確になったら、それを子どもたちや親にしっかりと伝えましょう。
宿題を減らす、なくすなど柔軟に個別対応する余地を残す
宿題の目的を子どもと保護者で共有した上で、その目的に沿った形で宿題について柔軟に個別対応する余地を残しておきましょう。
- 学習塾に通っている子
- 熱心な保護者が家で独自に学習を進めている子
- その他の習い事などで十分な家庭学習の時間が確保できない子
など、多様な子供がいます。あくまでベースとして一律に宿題を出す場合でも、一人ひとりの様子を見ながら柔軟に個別対応することは重要です。私も実際過去には、
- 受験対策に専念したい子には学校からの宿題は出さない
- 終末に宿泊でスポーツ大会に参加する子には、その週の宿題は出さない
などの対応を、保護者の方と相談の上したこともあります。私は当然の対応かなと考えていますがいかがでしょうか?
この記事の「宿題をしない子供への対応」という点からは一見関係のないように感じるかもしれませんが、このような姿勢をしっかりととっていくことは、子どもたちが日頃から目的を明確にして学習を進めていくことにもつながっていきます。スポーツ大会参加のために宿題を出さない対応をした子は、その分平日の宿題を頑張ろうと思ってくれたようで、平日の宿題への取り組みの質が向上していました。
子どもが自ら考えて行動する力をつけることを大切にして日頃から学級経営する
宿題の目的をしっかりと伝え、子どもたちがそれを理解したとしても、宿題を実際にするのは子どもたち自身です。
宿題は基本的には家で個人で取り組むものですから、子供たちが自身が自分で考えて主体的に取り組まなければなりません。
自分で考えて主体的に行動する力は一朝一夕には身につきませんから、日頃から鍛えておく必要があります。以下は、私が実践している「自ら考える力を伸ばす」ための学級経営のポイントです。もしよければ参考にしてみてください。
子どもが自ら進んで学びたくなる授業を日頃から実践する
子供たちが宿題にしっかりと取り組むには、学校の授業で学習内容に興味関心をもたせ、子供が自ら学びたくなるようにしていくことが大切です。
口で言うのは簡単ですが、それが簡単にできたら苦労はしませんよね。私も、日々試行錯誤しながら少しでも子供たちが学習内容自体を「面白い!」と思ってくれるように工夫しています。
以下は、私の専門である算数・数学について子供たちに「面白い!」と思ってもらえるような授業で使える豆知識などをまとめた記事です。もしよければ参考にしてみてください。
まとめ
この記事では、小学生・中学生の親と教師の立場から、宿題をしない子供への対応をどのようにしたらよいかについて書いてきました。
親も教員も、「子どものため」という認識をしっかりともった上で、子供たちのためになるような対応を心がけていきたいものです。
最後までお読みいただきありがとうございました。