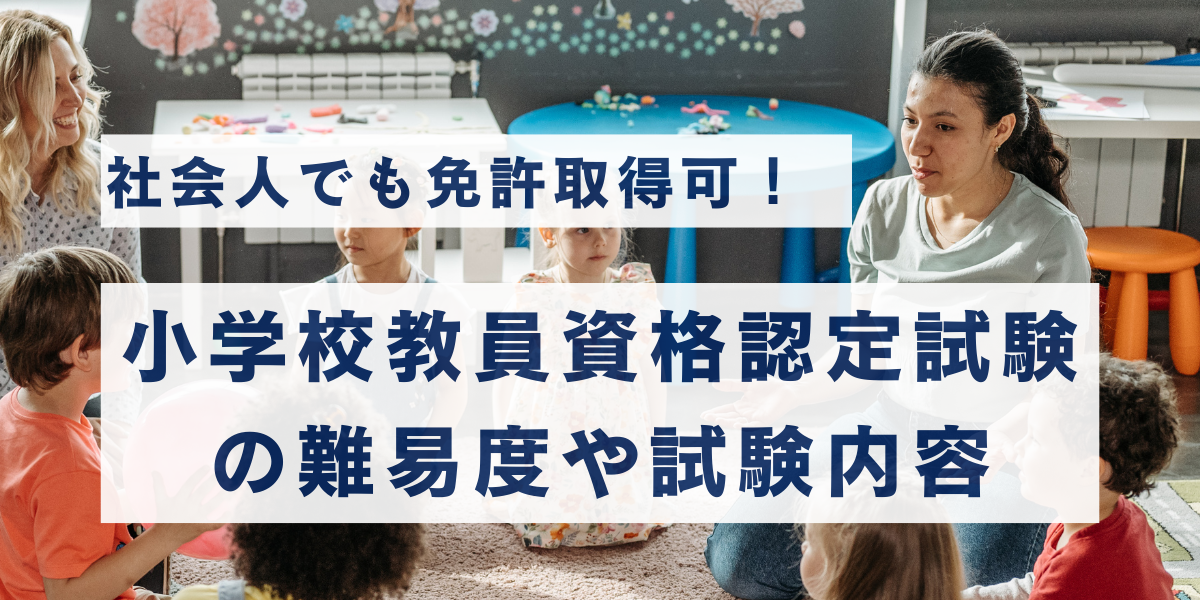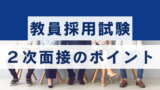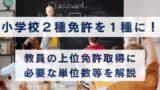私は、小学校教員免許を「小学校教員資格認定試験」に合格して取得しました。
一般的には教員免許は四年生大学で単位取得したり、通信制の大学に通ったりして取得します。この場合、取得には2年から4年程かかる上金銭的負担も大きいため、社会人から免許取得するハードルは高いと思われがちです。
しかし、この記事で紹介する「教員資格認定試験」に合格すれば、大学に通わず、短期間で、安く、教員免許状を取得できます。
この記事では、
- 教員を目指す社会人の方
- 自分が通う大学では教員免許を取得できないが教員を目指したい大学生の方
- 小学校教員免許を取得したい、他校種の教員の方
などに向けて、「小学校教員資格認定試験」について、難易度や試験内容について解説していきます。
社会人が免許取得するには通信制大学で単位取得するのが一般的
まずは、社会人が免許取得するには通信制大学で単位取得するのが一般的であることは基本としておさえておきましょう。
通信制大学で単位を取得することで確実に教員免許状を取得できますが、
- 期間が2年程度かかることもある
- 授業料は20〜40万円程かかる
などのデメリットもあります。
なお、通信制大学で教員免許状を取得しようとした場合には、取得できる免許状が限られていることが多いため、その点も注意が必要です。
通信大学で教員免許を取得しようとする場合には次の記事がおすすめです→大学卒業後に教員免許は取得できる!社会人になってから先生になりたいと思った(外部リンク)
小学校教員資格認定試験とは?
通信制大学で単位取得する以外にも教員免許状を取得する方法があります。それが「教員資格認定試験」です。しかも、
- 単位取得が不要で試験のみで取得できる
- たったの3日間(試験日程)の期間で取得できる
- 必要は金額はトータル数万円程度
と、通信制大学で取得することと比べても比べ物にならないほど大きなメリットがあります。
ここからは本題である「小学校教員資格認定試験」について解説していきます。
文部科学省が開催する試験
「教員資格認定試験」は、試験によって教員免許を取得することができる、文部科学省認定の試験です。
教員資格認定試験は、広く一般社会に人材を求め、教員の確保を図るため、大学等における通常の教員養成のコースを歩んできたか否かを問わず、教員として必要な資質、能力を有すると認められた者に教員への道を開くために文部科学省が開催している試験です。
文部科学省ホームページ
平成30年度からは、教員資格認定試験の実施に関する事務を、独立行政法人教職員支援機構が行うこととなりましたが、実質的にはこれまでと変わりません。
取得できる教員免許状は幼稚園、小学校、高校(情報)
文部科学省認定の教員資格認定試験で取得できる教員免許は
- 小学校教諭2種
- 幼稚園教諭2種
- 高等学校教諭1種(情報)※令和6年度試験より再開
の3種類です。この記事では小学校教員免許の取得を中心にお伝えしますが、その他に「幼稚園教員免許」、「高等学校教員免許(情報)」も取得できる点はおさえておきたいところです。
特に、高等学校の情報科教員免許は、過去に停止されていた試験が令和6年度試験より再開されたため、高校情報の免許取得を目指す方にとっては選択肢が広がることとなりました。
逆に、特別支援学校(自立活動)教員資格認定試験については、令和6年度以降は当面休止するとのことです。ただ、高等学校(情報)のように、今後再開する可能性もありますので、諦める必要はないと思います。
小学校教員資格認定試験の合格率
そんな「小学校教員資格認定試験」ですが、気になる合格率は以下の通りです。
試験を行っている独立行政法人教職員支援機構のホームページによると、「小学校教員資格認定試験」のここ数年の合格率は、
- 2018(平成30)年度…13.2%
- 2019(平成31,令和元)年度…31.8%
- 2020(令和2)年度…22.5%
- 2021(令和3)年度…21.7%
- 2022(令和4)年度…17.3%
- 2023(令和5)年度…22.0%
- 2024(令和6)年度…24.0%
となっています。(データ元:独立行政法人教職員支援機構ホームページ)
私が受験したのは今から10年以上前ですが、その頃から合格率は毎年同じように推移しています。この合格率から見てもわかる通り、年によってばらつきはあるものの、決して簡単とはいえないレベルです。
ただ、問題の傾向などは毎年ほとんど変わりません。そのため、きちんと対策すれば十分合格可能なレベルだといえるでしょう。
1次試験の試験内容と合格基準
ここからは、具体的な試験の内容と合格基準について書いていきます。競争試験ではなく、決められた合格基準を満たしたら合格という点がポイントです。
基本的に毎年傾向に大きな違いはありませんが、受験の際には最新の情報を確認してから臨むようにしましょう。
1次試験では、4つの科目の試験が行われます。そして、それら4つの科目全てに合格する必要があります。
教職専門科目に関する内容
教科及び教職に関する科目(Ⅰ)として位置付けられている内容です。
「教職専門科目に関する内容」の試験は、マークシートによる択一式のテストです。
内容は、いわゆる「教職教養」とよばれる分野から出題されます。基本的には、教員採用試験における「教職教養」の内容とほとんど同一と考えてよいでしょう。
この科目は、満点の6割以上が合格です。ですから、周りの受験生との順位は関係ありません。逆にいえば、6割の点数が取れなければ不合格となってしまいます。
教科に関する内容
教科及び教職に関する科目(Ⅱ)として位置付けられている内容です。
「教科に関する内容」の試験も、マークシートによる択一式のテストです。10科目の中から事前に6教科を選んで受験します。(「音楽」「図工」「体育」のうちから2教科以上を含めること)
出題内容は、「小学校の各教科の具体的指導場面を想定した指導法及びこれに付随する基礎的な教科内容」とされています。この説明だと何だかよくわからないかもしれませんが、
「学習指導要領に関する内容」と、「通常のその教科の内容」
が出題される、と考えていいと思います。それぞれの出題比率は教科によって異なりますが、
- 算数や理科、国語などは教科に関する内容が多め
- 体育や図工などの実技系の科目は学習指導要領の内容が多め
だったと記憶しています。受験する場合には直近の過去問等をよく確認し、対策を立てましょう。
この科目は、選択した6教科の満点合計の6割以上が合格です。ただし、選択した6教科のうち1教科でも最低基準(4割)に満たない場合は不合格となるため注意してください。
教科の指導に関する内容
教科及び教職に関する科目(Ⅲ)として位置付けられている内容です。
「小学校の各教科の具体的指導場面を想定した指導法及びこれに付随する基礎的な教科内容」を、論述式で解答します。10教科の中から1教科を選んで解答する形です。
私が受験した時には、算数を選択しましたが、
- この内容を指導する際に、どのように子どもに教えたらよいか?
- この学習を進める際に、気をつけることは何か?
というような内容を中心に出題される試験だったと記憶しています。受験当時大学3年生だった私は、教員としての経験はもちろん、教育実習の経験もありませんでしたが、「学習指導要領(解説編)」に掲載されている内容で対策できました。「学習指導要領(解説編)」には、細かな指導法まで記載されています。その内容を理解できていれば、十分合格可能です。
受験する場合には、自分が得意とする教科を事前に決めてその教科の「学習指導要領(解説編)」を使ってよく対策しておく必要があります。
この科目は、満点の6割以上が合格です。マークシート式ではないので、私が受験した時には、細かな採点基準などはわかりませんでした。
小論文
教科及び教職に関する科目(Ⅳ)として位置付けられている内容です。
「教職への理解及び意欲、児童理解、実践的指導等小学校教員として必要な能力等の全般に関する事項」に関する、論述式の試験です。
合格基準は至ってシンプルで、「A・Bの2段階評価とし、Aを合格とする。」とのこと。つまり、点数などではなく、シンプルに「合格か不合格か」ということです。
一般的な「小論文」の試験だと考えて差し支えないでしょう。以下に、令和6年度試験の実際の過去問題を紹介します。
問1.現在,我が国では,全ての児童の可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現が目指されている。こうした学びの実現が目指されている社会的背景を踏まえ,あなたは小学校教員としてどのような点に留意して授業を展開するか,300字以上400字以内で具体的に記述しなさい。
問2.「小学校学習指導要領」(平成29年文部科学省告示第63号)では,総合的な学習の時間において「自然体験やボランティア活動などの社会体験,ものづくり,生産活動などの体験活動,観察・実験,見学や調査,発表や討論などの学習活動を積極的に取り入れること」が求められている。児童を取り巻く環境や直接体験の意義を踏まえ,上記のような体験活動や学習活動を取り入れた探究的な授業の構想について300字以上400字以内で記述しなさい。
独立行政法人教職員支援機構ホームページ「令和6年度教員資格認定試験問題」
2次試験の試験内容と合格基準
1次試験を突破した後は、2次試験へと進みます。2次試験については、私が受験した頃とくらべて変更点が多いです。しかし、最新の募集要項等を私が読み、できる限り予測して説明していますので是非ご覧ください。
募集要項には2次試験は「教職への理解及び意欲、小学校教員として必要な実践的指導に関する事項」と位置付けられています。このことを踏まえて考えていくことが必要でしょう。
指導案作成・模擬授業
実施要項に記載されている「指導案作成」と「模擬授業」は、私が受験した時にはなかった試験科目です。そのため予想にはなってしまいますが、おそらく、多くの都道府県の教員採用試験で実施されている「指導案作成・模擬授業」とほぼ同じ内容なのではないかと思います。
私が実際に経験した試験を例に説明すると、
- 授業を実施する教科や単元が複数示される
- 「導入→展開→終末」といった枠だけが書かれたプリントが配付される
- プリントに授業の概要を記入する
- プリントを見ながら、試験監督を子どもに見立てて模擬授業をする
- 模擬授業後に模擬授業の内容について面接する
といったような試験内容です。都道府県によって違いはあるとは思いますが、対策は基本的に同じです。
基本的な対策としては、自分の得意とする教科の「学習指導要領(解説編)」をよく読み、そこで例示されているような流れで授業を展開できるようにしておくということだと思います。教員採用試験とは違って「選抜試験ではない」ため、学習指導要領から極端に外れたことをしなければ突破できる程度の合格基準なのではないかと思います。
口述試験(個別面接等)
口述試験は、私が受験した際にも実施されていました。
基本的には「教員採用試験」における面接試験と同じであると考えてよいと思います。採用試験の面接対策については以下の記事に書いていますので、是非お読みください。
合格基準
2次試験の合格基準については、
「複数課題について、総合的にA・Bの2段階で評価し、Aを合格とする」
という記載しかありません。科目ごと明確に示されていた1次試験とは異なり、科目ごとの採点基準は示されていません。とにかくベストを尽くすしかないでしょう。
小学校教員資格認定試験で免許取得することのメリット
最も早く安く教員免許を取得できる
「小学校教員資格認定試験」の最大のメリットは、取得にかかる期間が短く、とにかく費用が安いことだと思います。
例えば、通信制の課程で単位を取得する場合、通常2年程度はかかります。また、大学や教員免許の有無などにもよりますが費用はおよそ40万円程度です。
しかし、「教員資格認定試験」では、基本的に必要なのは受験料のみで、たったの約25,000円で教員免許を取得できます。
しかも、教員資格認定試験で免許状を取得する場合は、
- 1次試験(1日)
- 2次試験(1日)
のたった2日間で取得できるのです。
受験会場への移動などを考慮しても、他のあらゆる取得方法の中で、最も早く安く教員免許を取得できるといえるでしょう。
教員採用試験の対策と重なる部分が多い
受験対策の学習が、教員採用試験対策と重なる点が多いということもメリットと言えます。
教員免許状を取得しようとする方の多くは、教員になろうとする方がだと思います。教員になるためには、免許取得の他に教員採用試験に合格しなければなりません。
小学校教員資格認定試験と小学校教員採用試験の内容は重なる部分が多く、認定試験対策がそのまま採用試験対策にもなります。
教員資格認定試験のデメリット
一方で、デメリットにも目を向けておく必要があります。
他の取得方法と比べて難易度が高い
この記事の始めの方でお伝えした通り、「小学校教員資格認定試験」の合格率はおよそ10%〜25%程度で推移しています。
私が受験したのは今から10年以上前ですが、その頃から合格率は毎年同じように推移しています。この合格率から見てもわかる通り、年によってばらつきはあるものの、決して簡単とはいえないレベルです。
問題の傾向などは毎年ほとんど変わらず、対策はしやすいため、きちんと対策すれば十分合格可能なレベルだといえるでしょう。
とはいえ、大学の通信課程や大学で単位を取得して教員免許状を取得するなどの、他の取得方法と比べて難易度は高いです。
不合格なら教員採用試験の採用辞退となってしまう
教員資格認定試験を受験するにあたり、「取得見込みで教員採用試験を受験する場合」には注意が必要です。
通常、大学などに通って教員免許状を取得する場合、免許状の交付は卒業年の3月末となります。そのため、教員採用試験は免許状の「取得見込み」で受験することができます。
教員資格認定試験で免許状を取得しようとする場合でも、この「取得見込み」での受験が認められているのです。
これはつまり、せっかく採用試験に合格できても、資格認定試験に合格できなければ採用辞退せざるを得ないということを意味します。実際に私のまわりでも、「教員採用試験には合格できたが、教員資格認定試験には合格できず採用を辞退せざるをなかった」というケースがありました。
この記事の中でもお伝えした通り、試験は決して楽ではありません。教員採用試験と教員資格認定試験を同じ年に受験することはかなりのリスクであると考えられます。
取得できるのは「2種」免許状
小学校教員資格認定試験で取得できる教員免許状は、1種ではなく2種免許状であることにも注意が必要です。(※高等学校情報は1種)
通常の勤務では問題になることはありませんが、教職大学院への進学を希望する場合など、1種免許状が必要になるケースも無いとは言い切れません。ただ、そのようなケースは稀であり、2種免許状を1種免許状にすることもできますので、大きなデメリットではないでしょう。2種免許から1種免許にするための方法については、以下の記事で詳しく書いています。
最後に
ここまでお読みいただきありがとうございました。
教員の働き方改革の遅れや、教員人気の低下による教員不足などがニュースで取り上げられる中ではありますが、教員という仕事は本当に素晴らしいと感じています。教員という仕事に興味をもち、こうして免許を取得しようとこの記事を読んでいただいていること、とても嬉しいです。
これをお読みの皆さんが無事に教員免許を取得し、採用試験に合格され、共に働ける日を楽しみにしています。この記事が、少しでも皆様のお役に立てたなら幸いです。