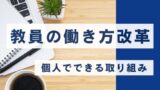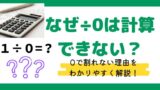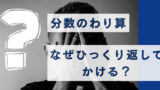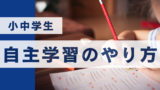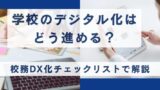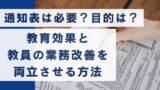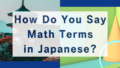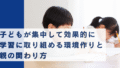教員は、子どもの成長に寄り添うことのできる職業です。少なくとも私はそのように感じて、これまで教員として勤務してきました。
しかし、一部の報道やインターネット上では、教員の働き方に対して、ネガティブな声が多く聞こえてきます。それらの意見については、その通りだというものもある一方、多くのものが、少なくとも私の周りの現実とはギャップがあると感じています。
これは、教員を目指す方のキャリア決定に悪影響を及ぼしているのではないかとも感じます。
そこでこの記事では、教員を目指している方、教員をキャリア形成の視野に入れている方、などに向けて、小学校教員として勤務している私の「リアルな一日」をお伝えします。
- 受け持つ学年や業務内容によって多少は負担が異なる
- 小学校教員のリアルな一日
- 7:45 出勤
- 8:15 担任クラスの教室へ 8:20から朝の活動
- 8:35 朝の会・健康観察
- 8:45〜9:30 授業(1時間目)
- 9:35〜10:20 授業(2時間目)
- 10:20〜10:40 子供の休み時間は休憩にあてる
- 10:45〜11:30 授業(3時間目)
- 11:35〜12:20 授業(空き時間)
- 12:20〜13:00 給食指導・昼食
- 13:00〜13:20 昼休み(休憩)
- 13:20〜13:35 清掃指導
- 13:40〜13:55 ドリル学習の指導
- 14:00〜14:45 5時間目(テスト)
- 14:50〜15:35 授業(6時間目)
- 15:40〜15:50 帰りの会
- 16:00〜16:10 休憩
- 16:10〜16:25 会議
- 16:25〜16:40 情報主任としての業務
- 16:40〜17:10 研究主任としての業務
- 17:10〜17:30 授業準備
- 17:30 退勤
- 最後に
受け持つ学年や業務内容によって多少は負担が異なる
まずは、私の校内での立場(役職)等をお伝えしておきます。この記事でお伝えする「リアルな1日」当時の私は、
- 小学3年生担任
- 研究主任
- 情報主任
などの業務を担っていました。
過去の経験上、担任業務は5,6年生担任が業務量が多いです。3年生は学年業務としては比較的負担が小さいですが、その分私は業務量が多い「研究主任」「情報主任」という立場をになっていました。校内全体で比較すると、平均より業務量は多いのかなと自覚しています。
これらを踏まえた上で、以下の「リアルな一日」をお読みいただければと思います。
小学校教員のリアルな一日

ここからは実際に、小学校教員として勤務する私の「リアルな一日」をお伝えしていきます。
7:45 出勤
私の勤務校では、出勤時刻は8時20分と定められています。しかし、子どもたちが学校に入ることができる(開門する)時刻が7時50分となっているため、私はそれまでに出勤するようにしています。職員の出勤時刻よりも早くに開門することは問題視されている部分です。実際、私も問題だとは思います。慣習として多くの学校で行われていることですが、なかなか変わっていかないのが現状です。これも現場の「リアル」です。
出勤したら、私はまずその日のスケジュールとタスクをチェックします。スケジュール管理とタスク管理が業務改善に欠かせないと考えている理由については、以下の記事で書いていますので、お読みください。
8:15 担任クラスの教室へ 8:20から朝の活動
8時20分から子どもたちの朝の活動が始まるため、8時15分ごろには担当クラスの教室に移動します。子供たちは8:20から読書の時間です。
私がまずやる事は、子どもたちの出席状況の確認です。私の勤務校を含め、今は多くの学校が欠席連絡を保護者がアプリで登録し、学校側がその情報を受け取ります。アプリの導入で随分と業務改善が進んできました。欠席の連絡がないのに登校していない児童がいた場合には、保護者に直接連絡をとって確認することもあります。子どもの安全管理という意味で重要な業務だからです。
その後は、子どもたちの宿題をチェックします。宿題チェックというと、1問1問丸つけすることをイメージされるかもしれません。しかし私の場合は、そうではありません。私は、宿題の丸つけと直しは子どもが自分でやるように指導しています。そして、子どもの学習方法をチェックし、アドバイスするように心がけています。
丸つけと直しについては、以下の記事で詳しく書いていますので、もしよければお読みください。
上の記事のやり方でやれば、教師が1問1問丸付けをする必要がなく、宿題チェックにはあまり多くの時間がかかりません。また、この方が子供たちの力にもなると考えています。
8:35 朝の会・健康観察
8時35分になると朝の会が始まります。ここで大切なのは、子どもたちの健康観察です。出席の確認はもちろん、その日の体調なども簡単に確認します。
その他、今日の予定についてなど、必要な話があれば子どもたちに話をします。
8:45〜9:30 授業(1時間目)
8:45〜9:30は1時間目の授業です。この日の授業は、算数でした。
基本的には教科書を中心に学習を進めます。私の専門とする教科は、算数数学ですので、教科書の内容に様々な工夫をして授業をすることが多いです。
この日の授業では、掛け算の筆算のやり方について確認した後、「なぜそのようにやると答えが求められるのか?」について、クラス内で議論を進めるような授業を展開しました。
このように、なぜそうなるのかを考える授業づくりを私は大切にしています。以下の記事の内容はその中のほんの一例です。もしよければお読みください。
9:35〜10:20 授業(2時間目)
9:35〜10:20は2時間目の授業です。この日は、国語の授業でした。物語分の学習です。文章から、主人公の心情を読み解く授業を行いました。私は小学校教員ですので、自分の専門とする教科以外も担当します。

様々な教科を教える事は大変だと思われるかと思いますし、実際簡単なことではありません。しかし、私の場合は算数数学の授業が軸となっており、国語などのその他の教科も算数数学の授業づくりと同じような形で組み立てています。一定のパターンを獲得できれば、どの教科の授業づくりも一定の事項をもとに考えることができ、負担は減ってきます。
10:20〜10:40 子供の休み時間は休憩にあてる
10時20分からは約20分間の休み時間です。
かつて私は、できるだけ子どもたちと一緒に遊ぶ時間を取るようにしていました。これは単に、子どもたちと遊ぶのが好きだからではなく、遊びの中で、見えてくる人間関係を確認したり、子供たちとの人間関係を築いたりすることの重要性を感じていたからです。
それ自体は否定しませんが、今は「自分自身の休憩にあてる」ようになりました。ときには意図的に子供との時間をとることもありますが、その後の授業へのパフォーマンスを向上させることが私にとっても子供たちにとってもプラスになると考えるようになったからです。
学校として「休み時間には子どもと遊ぶ」と決められているわけでもありません。昔は「教師たるもの休み時間も子供と触れ合うべし」という風潮がありましたが、最近はそのような風潮は無いように思います。
10:45〜11:30 授業(3時間目)
10:45〜11:30は3時間目の授業です。この日の3時間目の授業は、社会でした。
私は、社会科の授業では資料として「NHK for school」の動画を活用することが多いです。既成の動画を授業で積極的に活用することで、授業準備を効率化させるだけでなく、子どもたちの興味関心も高めることができます。
社会科を専門とする教員の方からすれば邪道な授業づくりなのかもしれませんが、小学校教員としてすべての教科を完璧に作ることは不可能です。メリハリをつけていくのも大切なことだと私は思います。作り込む授業もときには行いますが、日々の業務時間の中で毎日は難しいので、バランスを考えながら行なっています。
11:35〜12:20 授業(空き時間)
11:35〜12:20は4時間目の授業です。この日の授業は音楽でした。私の学校には、音楽を専門に教えるいわゆる音楽専科がいます。授業はその音楽専科に任せ、自由に使える時間として確保します。教員はこうした時間を「空き時間」などと呼びます。
私が過去にいた小学校では、「専科の授業にも担任が顔を出すべき」という風潮がある所もありました。しかし、そうした学校は稀ですし、それは間違っていると思います。担任も専科も同じ学校の職員としてて子どもたちの指導にあたるわけですから、担任が専科に「お願い」して指導してもらう訳ではないからです。
この日の私は、この空き時間を使って、週末に配付する学年通信の作成を行いました。私は学年通信の作成には細かいこだわりがありません。強いていえば、「こだわらない」というこだわりは大切にしています。保護者にとって必要な情報だけを端的に記載するので、15分程度、長くても30分程度で完成します。
12:20〜13:00 給食指導・昼食
12:20〜13:00は、給食指導および自分の昼食です。
給食指導といっても、こちらからあまり積極的に子どもたちに何かを働きかけていくことはしません。私は、個人的には児童生徒の食事に対して過度に介入すべきではないと考えています。もちろん、大声を出したり、立ち歩いたりするなどは注意しますが、「残食ゼロ」のようなことは特に何も言いません。
給食時の業務で大切なのは、
- アレルギー対応の児童の給食が、確実に間違いなく提供されているかの確認
- 食品の喉への詰まらせなど、安全面での対応
この2つくらいなのかなと感じています。その他は、子どもたちと会話を楽しみながら、自分も給食を食べてある程度リラックスして過ごします。
13:00〜13:20 昼休み(休憩)
13:00〜13:20は昼休みです。子どもたちは元気に遊びに出掛けていきますが、私は職員室で食後のコーヒーを飲んだり、歯磨きをしたりして過ごします。
以前の私は全く休憩を取らず、さまざまな業務を行なったり、子どもたちと遊んだりしていたこともありました。しかし、最近では意識的にしっかりと休むことを心がけています。その方が結果的に午後のパフォーマンスが向上したという実感があります。
もちろん、子どもたち同士のトラブルや怪我などがあった場合にはそちらを優先させますが、意識すれば意外と休めるものです。
13:20〜13:35 清掃指導
清掃の時間には、子どもたちと一緒に清掃に取り組みます。清掃のやり方を細かく指導する場面というのはあまり多くなく、子どもたちと一緒に清掃に取り組んでいます。
13:40〜13:55 ドリル学習の指導
私の勤務校では、ドリル学習等に取り組む時間がこの時間に設定されています。私のクラスではこの時間を活用して、計算ドリルや漢字ドリルに取り組むことが多いです。
また、週に1度程度、子どもたちが自分で学習する内容を選んで取り組む、自主学習の時間として活用しています。自主学習のやり方や指導法等については、以下の記事をお読みください。
14:00〜14:45 5時間目(テスト)
14:00〜14:45は5時間目の授業です。この日は、テストを実施しました。
私は、
- 子どもたちへの即時フィードバックにより学習内容の定着
- 採点業務を授業時間内に終わらせることによる業務負担軽減
という2つの理由から、提出した子のものからテスト採点を随時進め、基本的には授業時間内に子どもたちに返却するように心がけています。それについては、以下の記事でも触れていますのでお読みください。
14:50〜15:35 授業(6時間目)
この日の6時間目の授業は、図工でした。
子どもたちが、与えられた題材について自由に作品作りを進めます。
カッターナイフなどを使う活動の際には、安全対策をしっかりと行うよう心がけます。
15:40〜15:50 帰りの会
6時間目の授業が終わると、帰りの会です。
私は、帰りの会ではあまり長々と話さないことを心がけています。子どもたちが「早く帰りたい!」と思っている所に、ダラダラと話をしても伝わりません。特別なことがない限り、必要な連絡だけを済ませて帰りの会は早く終わらせます。
その方が、子どもたちにとっても教師にとっても、その後の時間を有効に使えるでしょう。
16:00〜16:10 休憩
子どもたちが下校した後は、軽く休憩して次の業務に備えます。
16:10〜16:25 会議
毎日打ち合わせがある訳ではありませんが、この日は他の先生との会議がありました。
自分から提案をする時には、
- 何についての提案か?
- その活動の目的は何か?
- この会議の場で検討したい点はどこか?
- 今後どのようなスケジュールでそれを進めていくか?
という点については自分の中で整理して資料を用意するようにしています。その資料も、デザインには一切こだわらず、A41枚に収まるように端的にまとめています。そうすることで論点が明らかになり、短い時間で会議がスムーズに進むようになります。
16:25〜16:40 情報主任としての業務
会議の後は、情報主任としての業務を行いました。
情報主任としての業務は、児童のタブレット端末や校内のICT設備の管理など様々なものがありますが、私が現在重点的に取り組んでいることは、ICT活用による校内の職員全体の業務改善です。以下の記事のものはその一例です。このような内容について、職員に周知し、学校全体の業務を効率化させることを考えて活動しています。
16:40〜17:10 研究主任としての業務
その後は、研究主任としての業務を行いました。
研究主任としての業務も情報主任と同様、多岐に渡りますが、この日の業務は校内の「通知表作成」についての提案書作成でした。
通知表を出す目的を整理した上で、簡素化できるところは簡素化して業務改善にも繋げることが狙いです。通知表を廃止するという考え方もありますが、私は、
「指導要録の作成義務がある今の現状では、できるだけ通知表の記載内容を指導要録と重複するようにし、指導要録は通知表のデータをスライドさせて完成させる」
という形がいいのではないかと考えています。それについては以下の記事で詳しく書いていますのでもしよければお読みください。
この提案の後、校内で検討を重ね、実際にそのような形で運用することとなりました。私を含め、ほとんどの職員から、「負担が大きく減った」という声が聞かれました。職員に貢献できる仕事ができたという達成感があります。
17:10〜17:30 授業準備
次の日の授業準備をします。
私は、日々の授業では
- 目的(ねらい)
- そのためにどのような活動を仕組むか
という点はどの授業でも明らかにするよう心がけています。本来はもっと授業準備に時間をかけたいところですが、日々の忙しさの中で時間の確保が難しいのが現状です。
17:30 退勤
最後に、メールの確認等をして退勤します。
私は毎日、およそ17:30〜18:00位に退勤するのが普通です。
17:30〜18:00頃退勤というのは、「早い」と感じるのか「遅い」と感じるのかは人ぞれぞれかとは思います。しかし、一部報道やSNSなどで言われるような「超ブラック」という印象は受けないのではないでしょうか?
最後に
ここまで、小学校教員として勤務する私のリアルな一日についてお伝えしてきました。
もちろん、生徒指導上の問題や保護者への対応など、突発的なことが起きる場合もあります。学校や割り当てられる業務内容によってはもっと退勤時間が遅くなってしまうケースもあるでしょう。私にも、過去、そのような経験をしたことはあります。今では考えられないような働き方をしていたこともあります。
しかし、そういった学校ばかりではないということもこの記事を通じてご理解いただけたらと思います。決して珍しい学校なのではありません。
この記事が、皆様のお役に少しでも立てたなら嬉しいです。最後までお読みいただきありがとうございました。