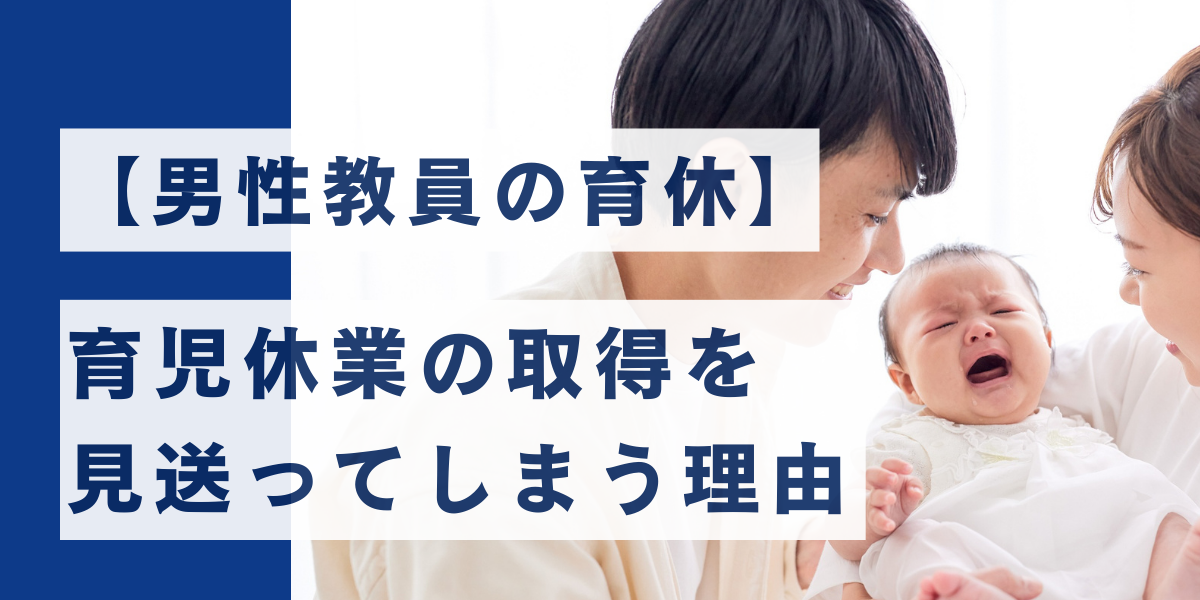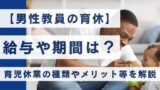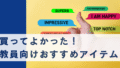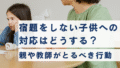男性の育休取得が以前よりも進み、男性教員の育休についても関心が高まっています。男性も積極的に育休を取得すべきという雰囲気が高まりつつあります。
しかし、まだまだ男性教員の育休取得が進んでいないのも事実。実は私も、1人目の子が産まれた際に取得を検討したものの、最終的に取得を見送ってしまった1人です。
この記事では、男性教員が育休取得の取得を見送ってしまうことについて、当事者の立場から理由を書いていきます。私を含めて育休の取得を見送ってしまう理由は何なのか…?それを考えることが、これからの男性教員の育休取得率を高めていくことにつながると思うからです。
私自身、2人目が産まれる際には育休取得を再検討しています。同じように、育休取得を検討している方の情報の1つとしてお役に立てたら嬉しいです。
男性教員の育休取得率は9.3%
文部科学省「令和3年度公立学校教職員の人事行政状況調査」によると、
令和3年度に新たに育児休業等を取得可能となった職員のうち、育児休業の取得割合は、男性が9.3%、女性が97.4%
とのこと。データが少し古いので、今はもっと高まっている可能性がありますが、女性と比べてとても低い現状があります。
男性教員が取得できる育休については以下の記事にまとめていますので、もしよろしければお読みください。
男性教員が育休取得を見送ってしまう理由
男性(教員に限らず広く)の育休取得が推奨される中、私を含めて育休の取得を見送ってしまう理由は何なのか…?それを考えることが、これからの育休取得率を高めていくことにもつながると考えています。
以下に、当事者である私の経験も踏まえながら、考えられる理由を挙げていきます。
現場への負担(代替教員の確保)が心配
現場への負担が心配ということが、育休取得を見送ってしまう理由の一つとして考えられます。
教員が育休を取得する場合、男性・女性問わず、代わりとなる教員が配置されます。代わりとなる教員のことを「代替教員」といいます。
年度途中で育休を取得しようとした場合の代替教員の確保が難しいと言われています。4月であればまだ確保はしやすいといいますが、年度途中ともなると話は別です。既に別の職場に勤務している可能性が高いからです。
「代替教員をやろうという意思はあっても、年度途中で今の職場を離れることに抵抗がある」
などの理由が考えられます。
対策として、文科省では令和5年度から、公立小・中学校の産休や育休予定者の代替教員を年度当初の4月から配置できるように運用を見直しました。新たな運用では、5月1日から7月末までに産休と育休の取得予定者がいる学校が対象となります。
このように対策が進む一方、4月から代替教員として採用されても、数カ月後に育休明けで教員が戻ってきたときには職を離れることになってしまうという問題もあり、まだまだ解決には至らなそうです。これはとても難しいことだと思いますが、育休を取得する職員と、代替教員として勤務する職員の双方にとってより良い制度設計が求められているといえます。
給与が減額される
子どもが 1 歳未満で「育児休業」を取得する場合、開始から180日間は標準報酬日額の67%、以後は標準報酬日額の50%が育児休業手当金として毎月支給されます。
そして、2025年4月から創設された「出生後休業支援給付金」により、実質育休取得前の水準と同じだけ受け取れるようになりました。ただし、一定の条件があるようですので、きちんと調べておく必要があります。
私が育休取得を検討していた際には、「給与の減額」というのが取得しなかった大きな理由でしたが、当時と比べてこの部分が改善されています。
また、ボーナス、昇給については、
- 期末手当と勤勉手当(ボーナス)は、休業前の勤務実績に応じて支給。 1 ヵ月以下の育休については、支給割合が減らない。
- 昇給については、復帰時に育休期間中も勤務していた場合と同じだけ昇給。(昇給延伸完全復元)
と定められています。
退職金に影響する
育休を取得することによって、多少ではありますが、退職金にも影響があります。
1 年目の取得期間については1/3を、残りの取得期間については1/2を在職期間(経験年数)から除いて計算されます。
実際に具体的な金額の計算はできていませんが、多少の影響があるということは理解した上で取得する必要はあるでしょう。
退職はまだまだ先の話とはいえ、考慮しておくことは大切です。
育休・産休に限らず日頃から休みやすくする環境づくりが大切
ここまで、男性教員が育休取得を見送ってしまう理由について書いてきました。育児休暇は、自分の大切な家族のためにも是非取得したいものです。
育休・産休に限らず、日頃から休みやすい環境づくりが大切だと考えています。それは、管理職を中心とした学校全体の取り組みはもちろん、日頃から個人でも取り組めることもあります。個人で取り組める取り組みについては、以下の記事で詳しく書いていますので、よければお読みください。
- 上記の記事で書いたような個人の取り組み
- 学校全体の取り組み
- 自治体の取り組み
- 国の取り組み
によって教員がもっと休みやすくなれば、結果として育休取得率の上昇にもつながると思います。
最後に
最後に、ここまで書いてきた内容を参考に、自治体や最新の動向等もチェックしながら各御家庭で判断してもらえると良いと思います。
私も、2人目が産まれるときにはどのようにするのか、家族とも相談しながら検討したいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。