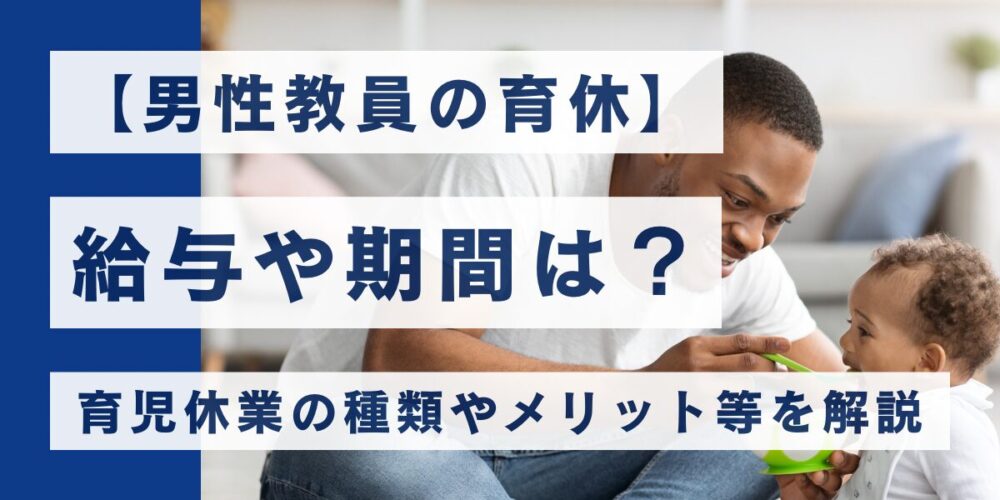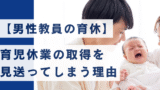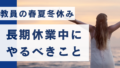男性の育児参加が当たり前となっている今、様々な企業等における男性の育児休業の取得が注目されています。もちろん、教員も例外ではありません。
しかし、男性の育休取得にあたっては、制度が複雑でわかりにくく、
- 「給与はどうなる?」
- 「どれくらいの期間とれるの?」
- 「各制度のメリットやデメリットは?」
など、取得にあたって不安や疑問をもつ方も多いでしょう。
そこでこの記事では、育休取得を検討している教員の皆さんに向けて、男性が取得できる育児休暇制度の「期間」や「その間の給与」、「メリットやデメリット」などについて詳しく解説していきます。
日本の男性教員の育休取得率は?

まずは、日本の男性教員の育休取得率はどのくらいなのかを確認しておきましょう。
文部科学省「令和3年度公立学校教職員の人事行政状況調査」によれば、男性教員の育休取得率は9.3%です。
令和3年度に新たに育児休業等を取得可能となった職員のうち、 育児休業の取得割合は、男性が9.3%、女性が97.4%で、前回調査(平成30年度男性2.8%、女性96.9%)から増加。
文部科学省「令和3年度公立学校教職員の人事行政状況調査」
一方、一般企業なども含めた日本の男性全体の育児休業取得率は13.97%です(厚生労働省が「令和3年度雇用均等基本調査」で公表)。日本全体の男性育休取得率が低い中、教員の場合には日本全体と比較してもさらに低い取得率であるといえます。
男性教員の育休取得率が低いことに関しては以下の記事で理由を書いていますので、もしよければお読みください。
男性教員が取得できる育児休暇制度
ここからは、男性教員が取得できる育児休暇制度について1つ1つ具体的に解説していきます。
「育児休業」

まず基本となる「育児休業」について確認しましょう。「育児休業」とは、一定期間完全に休みをとって育児に専念できる休暇制度です。いわゆる「育休」と呼ばれるものです。この「育児休業」は、以下のように法律によって定められています。
第二条 職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の子を養育するため、当該子が三歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で条例で定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。
地方公務員の育児休業等に関する法律 (一部略)
つまり、子どもが産まれてから 3 歳をむかえるまでの期間、2回まで育児休業をとることができるということです。これは、男女どちらでも取得が可能で、配偶者が育休中であっても取得できます。

完全に休みをとれるため、育児に専念できることが最大のメリットであるといえます。
育児休業中の給与(子どもが 1 歳未満の場合)
子どもが 1 歳未満で「育児休業」を取得する場合、開始から180日間は標準報酬日額の67%、以後は標準報酬日額の50%が育児休業手当金として毎月支給されます。
そして、2025年4月から創設された「出生後休業支援給付金」により、実質育休取得前の水準と同じだけ受け取れるようになりました。ただし、一定の条件があるようですので、きちんと調べておく必要があります。

また、ボーナス、昇給については、
- 期末手当と勤勉手当(ボーナス)は、休業前の勤務実績に応じて支給。 1 ヵ月以下の育休については、支給割合が減らない。
- 昇給については、復帰時に育休期間中も勤務していた場合と同じだけ昇給。(昇給延伸完全復元)
と定められています。
また、退職手当は育休期間のうち、 1 年目の取得期間については1/3を、残りの取得期間については1/2を在職期間(経験年数)から除いて計算されます。退職手当は、すぐに関係のあるものではないですが、考慮しておく必要があるでしょう。
育児休業中の給与( 子どもが1 歳以上 3 歳未満の場合)
子どもが 1 歳以上 3 歳未満で「育児休業」を取得する場合の給与は、基本的に無給です。ただし、下記の条件を満たせば育児手当金が支給されます。
- 「 1 歳までの育児休業制度」を両親ともに取得する際に、要件(下記参照)を満たした場合には、育児手当金の支給が 1 歳 2 ヵ月まで延長されます。(パパママ育休プラス制度)
- 保育所等の利用を希望し、申込みを行っているが 1 歳に達した日の後も入所できない時。※
- 子の養育を予定していた配偶者の死亡・または負傷・疾病または身体上若しくは精神上の障害により、子の養育が困難な時。※
- 配偶者の別居※
- 配偶者の産前産後休暇※
※については、子が 1 歳に達した日後について 1 歳 6 ヵ月まで、次に子が 1 歳 6 ヵ月に達した日後についてなお該当する場合に 2 歳まで延長されます。
パパママ育休制度の要件は以下の通りです。
- 配偶者が子が 1 歳に達するまでに育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が子の 1 歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日は配偶者がしている育児休業の初日以降であること
育児休業中は代わりの職員が配置される

育児休業取得中は、休業を取る職員の代わりに、職員が配置されます。
ただし、代わりの教員(講師)を探すのに時間がかかるため、早めに校長に相談しておく必要があります。
「部分休業」
次に確認しておきたいのは「部分休業」です。「育児休業」が一定期間完全に休みをとるのに対して、「部分休業」はその名の通り部分的に休みを取ることができる制度です。
小学校就学前の子どもを育てる(育児休業をとっていない)教職員は、 1 日 2 時間を限度に30分単位で部分休業を取ることができる制度です。
「時差勤務」や「育児時間(後述)」と併用して取得することが可能です(合わせて 1 日 2 時間まで)。また、毎日取得しなくてもよいため、それぞれの都合に合わせて取得することが可能となります。
部分休業中の給与は減額される
部分休業を行う場合には、取得日数等に応じて給料が減額されます。
減額の詳しい計算方法等は自治体などによるのかもしれませんが、単純に1ヶ月のうちで部分休業を取得した日数の割合でおよその計算ができるかと思います。
実際の給与計算については、「部分休業」の取得前に自治体や事務担当者によく確認するようにしてください。
部分休業中には代わりの職員が配置されない
「部分休業」を取得する場合には、「育児休業」とは異なり、代わりの職員は配置されません。そのため、子どもたちが下校した後の事務仕事の時間などを部分休業にあてることが基本となるでしょう。
また、朝の時間に部分休業を取得することも考えられますが、その場合にはその間代わりの職員に教室に入ってもらうなどが必要となります。
「育児時間」(特別休暇)
「育児時間」という制度もあります。「育児時間」は特別休暇という休暇に分類されます。「育児時間」は、3 歳未満の子どもがいる場合に、 1 日 2 回30分以内ずつまたは 1 回にまとめて60分以内の特別休暇をとることができるという制度です。ただし、年休などを使って勤務時間が 4 時間程度の時は 、1 回30分となります。
メリットは他の休業との併用が可能なことです。前述の「部分休業」や「年休」などと併用して取得することが可能です(合わせて 1 日 2 時間まで)。また、勤務時間のどこで取得しても構わないため、各自の都合に合わせて取得することが可能です。
前述の「部分休業」と似た部分が多いですが、以下の点については異なるため注意が必要です。
- 男女どちらでもとれるが、一人の子に対して夫婦が重複してとることはできない。ただし、両親で朝と夕方に分けてとることはできる。
- 配偶者が育時休暇中の場合は取得できない。ただし、配偶者が病気等で子どもの養育ができなかったり、介護があったりする場合は取得できる。
「育児時間」取得中の給与は減額される
育児時間でも部分休業と同様に、取得日数等に応じて給料が減額されます。
「部分休業」と同様、減額の詳しい計算方法等は自治体などによると思われますので、実際の給与計算については、「部分休業」の取得前に自治体や事務担当者によく確認するようにしてください。
「育児短時間勤務制度」

小学校就学前の子を養育している場合に取得できる「育児短時間勤務制度」は、以下の勤務形態から選んで勤務することができる制度です。
- 1 日 3 時間55分×週 5 日(週19時間35分)
- 1 日 4 時間55分×週 5 日(週24時間35分)
- 1 日 7 時間45分×週 3 日(週23時間15分)
- 1 日 7 時間45分× 2 日、 1 日 3 時間55分× 1 日(週19時問25分)
このため、勤務する時間を各自の都合に合わせて選択できることがメリットといえるでしょう。また、配偶者の状況によらず利用できる(両親が同時に利用することも可能)なため、夫婦で教員の方の場合にはより休み方の自由度が増します。
「育児短時間勤務制度」利用の場合の給与は減額される
この「育児短時間勤務制度」を利用する場合も、給与が減額されます。
その場合の給与の減額要件については以下の通りです。
- 給与は、勤務時間に応じて支給される。(つまり、減額)
- 期末手当と勤勉手当(ボーナス)、退職手当が一部除算される。
「育児短時間勤務制度」では子どもの小学校入学まで期間を延長できる

この制度を利用する場合には、1 ヵ月以上 1 年以内の期間で期間を設定します。子どもが小学校入学までは期間の延長が可能となっています。
ただし、一旦この制度の利用を停止した場合、原則として、再取得するためには 1 年以上の間を空けることが必要となります。(特別な事情があれば取得できることもあります)
「配偶者出産休暇」(特別休暇)
「配偶者出産休暇」は、妻が入院した日から、分べんの日後 2 週間目に当たる日までの間に 3 日以内の休みを取得できる特別休暇制度です。妻が出産する男性教員であれば全員が取得できる制度です。
「配偶者出産休暇」では給与の減額はない
「配偶者出産休暇」を取得した場合給与の減額はありません。イメージとしては「年休」が3日間多くなるという感じです。
もはや、メリットというよりも、取らない手はないともいえる休暇制度だといえるでしょう。
この休暇で出産の付き添いや出生の届出をするケースが多いと思われます。時間単位でも取得できる点もありがたいポイントです。
なお、婚姻の届け出をしていなくても事実上婚姻関係と同様であれば認められます。ただし、 妊娠4 ヵ月以上の出産に限ります。
「男性職員の育児参加のための休暇」(特別休暇)
「男性職員の育児参加のための休暇」は、配偶者の出産予定日の 6 週(多胎妊娠の場合は14週)以前の日から、出産後 8 週目の日までの期間において、5 日間以内の休みを取得できる特別休暇制度です。
出産予定日以前の6週間と出産後8週間の合わせて14週間(約3ヶ月)から取得日を選ぶことが可能です。
「男性職員の育児参加のための休暇」では給与の減額はない
この「男性職員の育児参加のための休暇」も「配偶者出産休暇」と同様に給与の減額はありません。
これは男性の育児参加を促進するためにできた制度で、妻が出産する男性教員全員が取得できます。「配偶者出産休暇」と同じく、取らない手はないといえる休暇制度でしょう。
各制度のメリットとデメリットのまとめ
ここまで紹介してきた各制度のメリットとデメリットをまとめます。
各制度のメリット
- 育児休業…①まとまった休みが取れるため育児にしっかり参加できる、②代わりの職員が配置されるため現場の負担を最小限に抑えられる
- 部分休業…①現場を離れることなく時短勤務が可能、②小学校就学時まで取得可能
- 育児時間…①現場を離れることなく時短勤務が可能、②30分単位での取得が可能
- 育児短時間勤務制度…①多様な勤務形態から自分に合ったものを選べる
- 配偶者出産休暇…①給与が減額されない(年休と同じように取得できる)
- 男性職員の育児参加のための休暇…①給与が減額されない(年休と同じように取得できる)、②出産前後約3ヶ月の期間から休む日を選べる
各制度のデメリット
- 育児休業…①給与が減額される、②早めの申告が必要
- 部分休業…①給与が減額される、②休みが短時間のみ、③代わりの職員がいないため現場の負担増
- 育児時間…①給与が減額される、②休みが短時間のみ、③代わりの職員がいないため現場の負担増
- 育児短時間勤務制度…①給与が減額される、②休みが短時間のみ、③代わりの職員がいないため現場の負担増
- 配偶者出産休暇…①出産前後の3日間のみ
- 男性職員の育児参加のための休暇…①取得できるのが5日間のみ
各制度を正しく理解した上で選択することが大切
ここまで、男性教員が取得できる育児休暇制度について具体的な制度をご紹介してきました。
どの休暇制度が良い悪いということではなく、各制度を正しく理解した上でそれぞれに合った選択をすることが大切です。それぞれの制度のメリットやデメリットを踏まえた上で、パートナーとよく相談して決めていく必要があると思います。
皆さんが育休の取得を検討するにあたり、この記事が少しでもお役に立てたなら嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。